[2025年7月27日 更新]
都立入試理科の傾向を見ていく。今回は「光の屈折」
都立入試では何度も出されている単元だ。
過去16年間で「光の屈折」が出題されたのは6回。
2025年度 大問1
2024年度 大問2
2020年度 大問2
2019年度 大問1
2017年度 大問2
2010年度 大問1
最近はよく出ている。
2年連続で出たこともあるので、2025年度も要注意だと思ってたら出た。
3年連続で出たことはないから2026年度は出ないだろう。
◆入射角、屈折角の関係は覚えなくていい
光が空気中→水中に進む場合と、水中→空気中に進む場合では入射角と屈折角の大きさの大小が逆になる。
だから「空気中の方が水中よりも角が大きくなる」とだけ覚えておけばいい。
そうすれば都立入試は楽勝である。
◆実際の問題を解いてみる
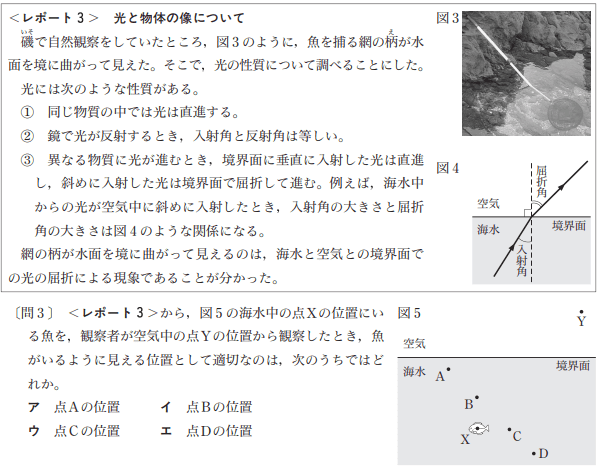
参照:都教育委員会HP
これは2017年度の都立入試。
図4がほぼ答えともいえるヒントになっている。この矢印を図5に当てはめれば、Yから境界面までの直線をそのまま延長すれば点Bとぶつかることが分かろう。
もちろん答えは「イ」だ。
これは学校のワークに載っているレベルの問題だ。特に難しくはない。
だが正答率は46.8%と低い。正しい受験勉強をしておらず「何となく」でやってきたんだろうね。もったいない。

